NPO法人ケアリフォームシステム研究会(CRS)は、リフォームだけに限定しない取組みをする、稀有で貴重な工務店の団体。
学校のプールで飛び込み頚髄損傷C・6でほぼ四肢麻痺の子があきらめていた料理作りを何度も話し合い、残存能力・潜在能力を引き出すことが住環境から出来ることを伝え実践。「一人で料理がしいたい」希望のキッチンを完成。1か月後「この子が作りました」とお菓子皿に盛ったクッキーを見せるお母さん「今まで介護が大変だった。新しい家は、ほとんどの日常生活動作が出来るようになり、介護がこんなに楽とは思いませんでした。娘は自分の家が一番楽しいと言っています。家の環境がいかに大切かを知りました。」
NPO法人ケアリフォームシステム研究会の創始者、名誉理事の武藤俊之氏が語ります。
目 次
VR展示場に映し出された住環境の可能性
独立という転機と福祉住環境への目覚め
ケアリフォームシステム研究会の設立とその挑戦
研究会を運営する上で大きな課題
研究会の着実な拡大と世界を見据えた未来への展望
住環境に悩みのある皆さんへ
関連記事、関連リンク
VR展示場に映し出された住環境の可能性

らくゆく編集者:
武藤先生、本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただきありがとうございます。
早速ですが、先日拝見いたしましたVR展示場は、本当に感銘を受けました。驚きと同時に大きな可能性を感じました。動画も非常に分かりやすく作られていて、これが多くの人に届くことを私たちも強く願っています。
武藤俊之氏(以下、武藤):
ありがとうございます。私たちがVR展示場という新しい技術を取り入れているのは、今住んでいる住宅から、高齢者向け、子育て世代向け、様々な障がい特性やニーズに応じたバリエーションに改装できることを知って頂き、「自分の家が一番いい」と心から思えるような住環境を、より具体的に分かりやすく、お客様にイメージしていただくためです。自宅に帰ってきたときに、「やっぱり自分の家が一番落ち着くなぁ、くつろげるなぁ」と感じていただけるような、そんな家づくりを大切にしています。
ある障がい者の方の住宅を造らせていただいた時に「ここまで考えてくれる工務店さんってなかなかいないね」「この家に居る時が一番幸せです」と言っていただいたんです。その言葉が、やってて良かったなと思えて、続けていく上での力となっています。お客様一人ひとりに寄り添う家づくり、これが私たちの変わらない考え方です。
独立という転機と福祉住環境への目覚め
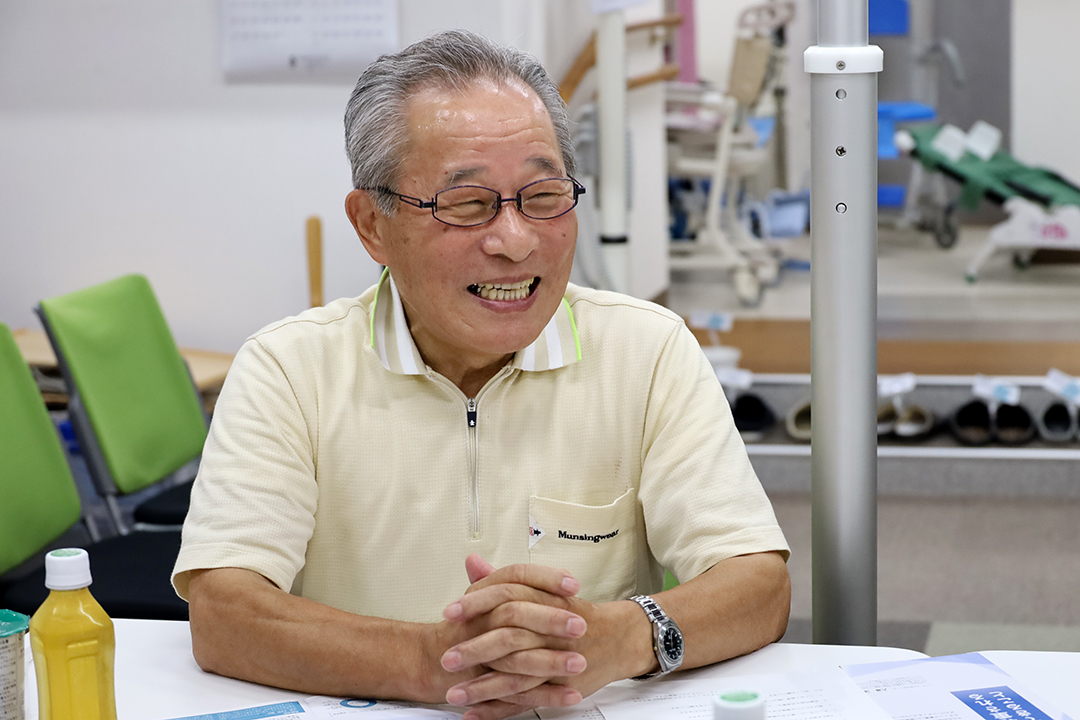
兄と13年間、一般住宅の工務店を営んでいたが独立を決意。独立時「他社に負けない専門知識と技術を身につけたい」と強く思っていた。1990年代初頭の高齢化社会への対応政策に着目し、「高齢者向けの住まいづくり」に特化して新たなスタートを切った。東京に車いすの方が体験できるモデルルームを案内してくれた若い担当者に「高齢者だけでなく、障がい者の幅広い年代で、それぞれの方々に応じた多様な住環境を考えた方が良いですよ」と指摘され、視野が広がった。高齢者向けだけでは限界があると感じ、障がい者全体に対応した住環境づくりに取り組むことを決意。地元の障がい者支援学校などに自ら働きかけ、積極的に活動を開始。「まだ誰もやっていない」という言葉に後押しされ、誰にも負けない障がい児・障がい者住宅の開発を始めた。
ケアリフォームシステム研究会の設立とその挑戦

様々な障害のある方の住環境に真剣に取り組み、7~8年が経過。全国に身体が不自由な方は多く、この活動を広げたいが、一人では限界を感じるようになった。LIXILやTOTOから、同じ思いを持つ工務店が全国にいるという情報が入り、地域の工務店に知識を伝えることで活動が広がると考えた。仲間意識を持てるよう、研究会「武藤塾」を立ち上げ現在27期を迎え、ノウハウや事例、体験談を会員同士で公開・共有している。研究会では会員から新しい知見も得られ、互いに学び合える場となっている。利益目的だけでなく、地域社会への貢献意識を持つ工務店が増えてきた。約12~13年後、武藤塾をNPO法人化。NPO法人として活動することで、会場利用や相談者の安心感などのメリットを感じている。
研究会を運営する上で大きな課題

武藤:
最も大きな課題は、この特別な知識をどのようにしたら全国の工務店さんに深く理解していただいて、実践して頂けるかということです。相談者一人ひとりの身体の不自由なところや、それぞれの住まいの状況はひとつずつ違いますから、それに合わせた福祉用具の取入れ方なども含めて、最適な提案ができる知識を身につけてもらう必要があります。
講義を受けて知識をつけたから仕事が来るのではなく、それは一つのきっかけで、具体的にはどのように動いたら障害のある方々と信頼関係を築き、連携がとれるのか、皆さんが考えていけるようになって頂きたい。会としては、営業、接し方、フォローなどの支援や、意見交換しながら進められる組織創りが、今の大きな課題だと考えています。
研究会の着実な拡大と世界を見据えた未来への展望
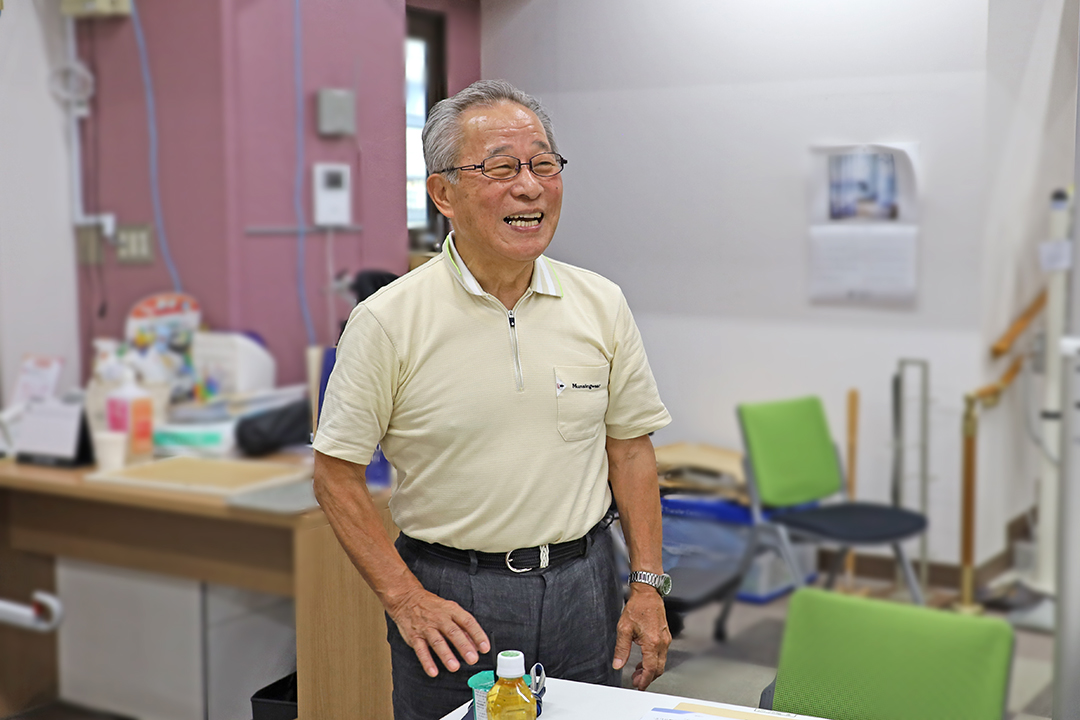
武藤:
私たちの現在の具体的な目標は、日本全国の47都道府県すべてに、当研究会に所属する工務店さんが3~4社ずついる体制を確立することです。現在はまだ東北や北陸など、会員数が少ない地域もありますので、これらの地域に積極的にアプローチし、ネットワークを拡大していきたいと考えています。
そして将来的には、日本国内に留まらず、世界へ向けて私たちの知識と技術を発信していきたいという壮大な夢を抱いています。先日NHKの方からも、海外に向けても情報発信を工夫してみてはどうか、という大変興味深いご提案をいただきました。特に韓国や東南アジアなどでは、まだ障害のある方の住環境整備が進んでいない国も多くあります。日本のこれまでの成功事例や知見を、国際的な視点から伝え、世界中の人々の生活の質の向上に貢献していきたいと考えています。
住環境に悩みのある皆さんへ

「自分が暮らしている家がすごく生活しやすい家だったら自立につながります」
武藤:
自立への意欲が出てくると思います。そのためには自分の要望を伝える。例えば体温調整が難しい人には、夏涼しく冬暖かい家づくりも今できています。そこから、外出するときのうまくいく方法とか、トイレとか、キッチンとか、それから入浴とか、一つ一つパターンを箇条書きにして、工務店さんに工夫してもらえませんかと依頼する。情報発信を自分からやられたらいいと思います。
工務店さんも何をやっていいかわからないんです。どういうお手伝いをしようか、言われたらしますというか…。お互い御本人さん工務店さんと意見交換ができて、いいものができる、そういう造り方ができたらいいかなと思います。
最後に、福祉先進国とされている北欧などと比較しても日本は進んでいる
武藤:
私は、日本は決して遅れているわけではない、制度としてはまだまだですが福祉用具機器はむしろ、日本の文化習慣に有った素晴らしものが多く進んでいると感じています。例えば、以前は国際福祉機器展に行くと、北欧メーカーの製品が中心で、日本の製品はあまり目立っていませんでした。しかし最近では、日本の気候や文化、住環境に合った細やかな配慮がなされた福祉用具を開発し、展示する日本のメーカーが非常に増えてきています。これは日本独自の強みであり、世界に誇れる点だと感じています。
らくゆく編集者:
本日は、貴重かつ大変示唆に富むお話を誠にありがとうございました。先生の今後のご活躍と、貴研究会のご発展を心よりお祈り申し上げます。
関連記事
関連リンク
身体が不自由な方とそのご家族の住まいのWEB展示場
CRSのホームページはこちら
CRSの加盟店についてはこちら
写真:小川 陽一 文:大道寺 清

